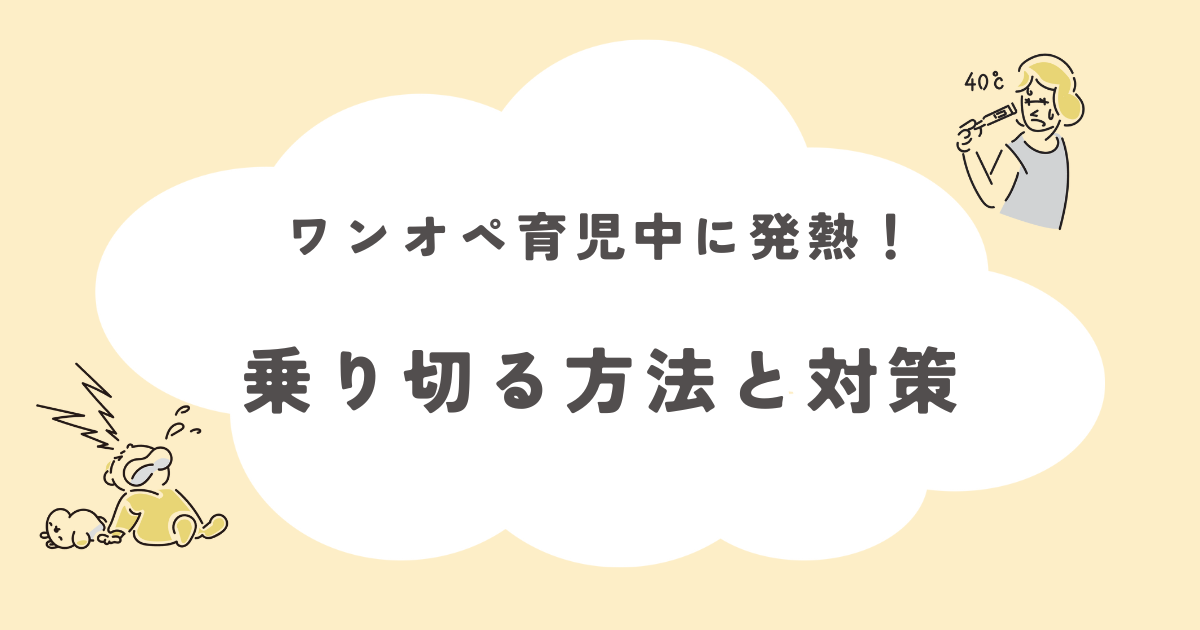ワンオペ育児中に自分が高熱を出してしまったら……。
誰にも頼れない環境では、自分が倒れるわけにはいかないというプレッシャーがのしかかります。
そんなときは気合いで乗り切るしかないのが現状ではないでしょうか。
しかし動けるうちは何とか家事や育児をこなせても、高熱になるとそれすら厳しくなることも。
さらには子どもが風邪を引いたあとに親にうつるパターンが多く、親はぐったり、でも子どもは元気いっぱいという状況に……。
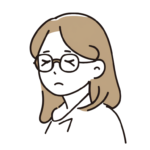 まりも
まりも子どもが未就学児となると対応がますます大変!
この記事ではワンオペ育児中に発熱したときの対処法と、負担を減らすために事前にできる対策についてご紹介します。
ワンオペ育児で自分が熱!乗り切る方法


ワンオペ育児で自分が発熱してしまったときは、最低限のことだけやってあとは休む!というスタイルで乗り切るのが1番です。
無理にすべてをこなそうとすると回復が遅れてしまいます。
体を休める環境を作る
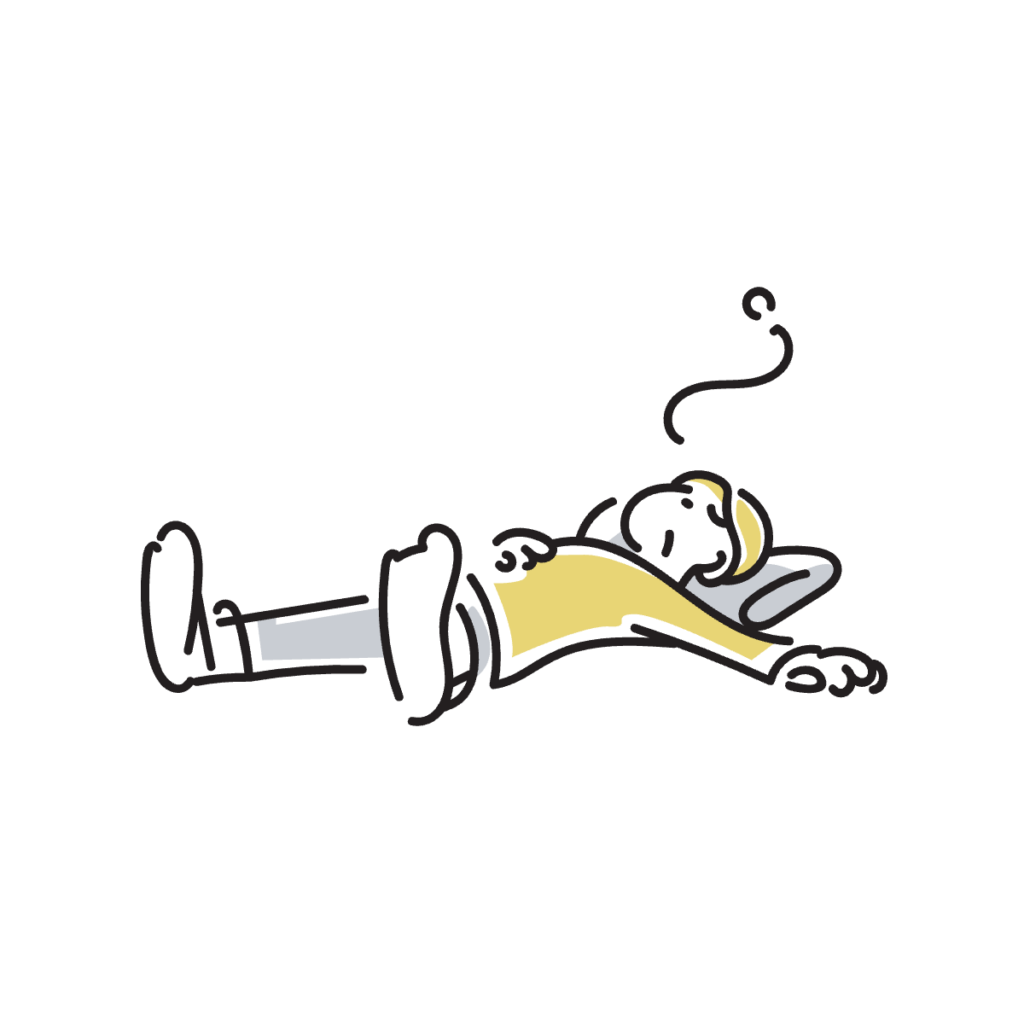
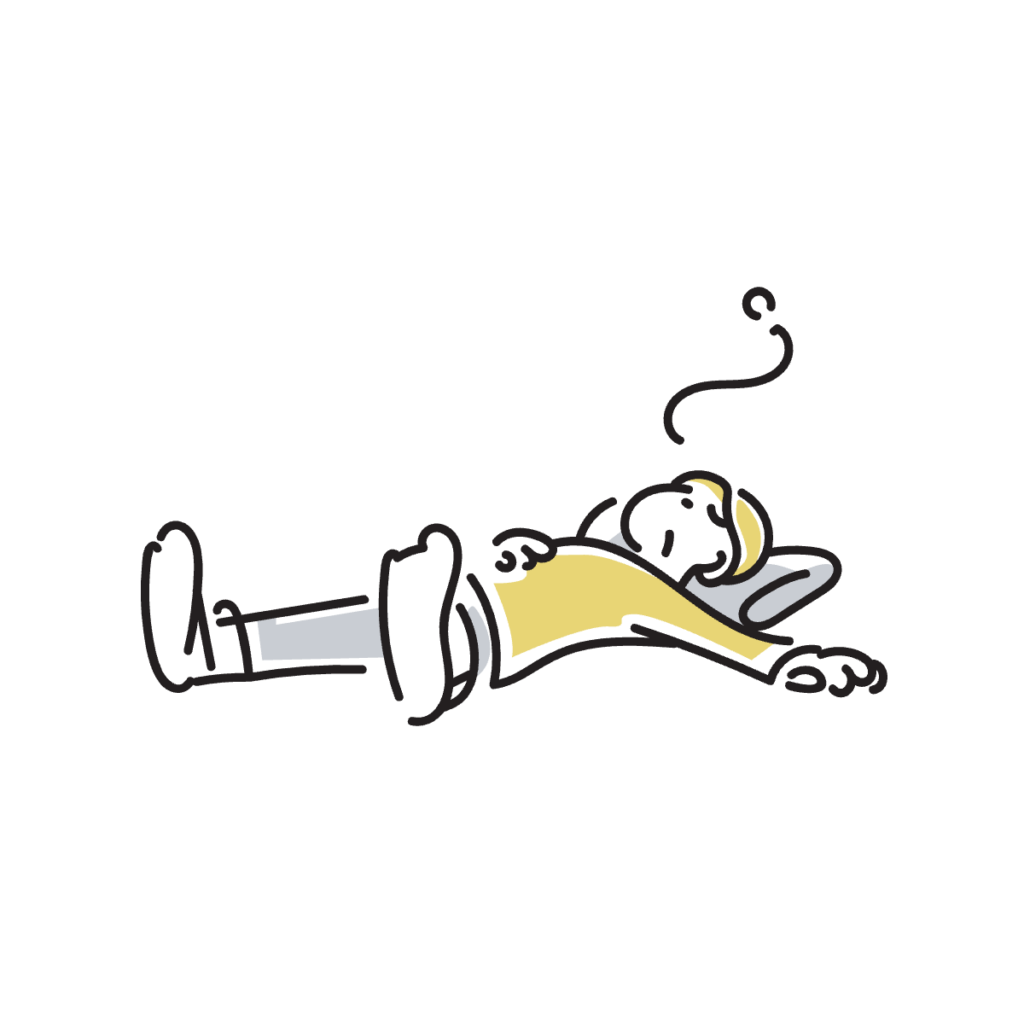
少しでも回復を早めるために、休める時間はとにかく横になることを最優先しましょう。
できるだけ動かずに済む環境を整えることが重要です。
リビングに布団を敷くことで、子どもの様子を見守りながら体を休めることができます。
とはいっても、小さい子どもがいる状況でゆっくり休むのは難しいですよね。
そんなときは最低限のことだけをするようにしましょう。
体調不良の日は最低限の育児だけ
🌱無理をせず、これだけやればOKと割り切ることが大切です。
- お風呂→数日入らなくてもOK
- ご飯→レトルトや冷凍食品などの非常食ですませる
- 子どものお世話→テレビ・動画配信に頼る
- 自分→できるだけ横になり、回復を最優先
1.お風呂


動くのもつらいときは、子どもをお風呂にいれるのはお休みしましょう。
でもなんとなく気になる……というときは、蒸しタオルやボディーシート、おしりふきなどで汚れている部分を軽く拭いてあげるだけでもスッキリします。
特におしりふきは赤ちゃんを育てている家庭なら常備しているアイテム。
手軽に使えるのでおすすめです。
普段体調がいい日のワンオペお風呂の入り方は、【体験談】ワンオペ2人育児 赤ちゃんと上の子をお風呂に入れる方法で紹介しています
2.ご飯
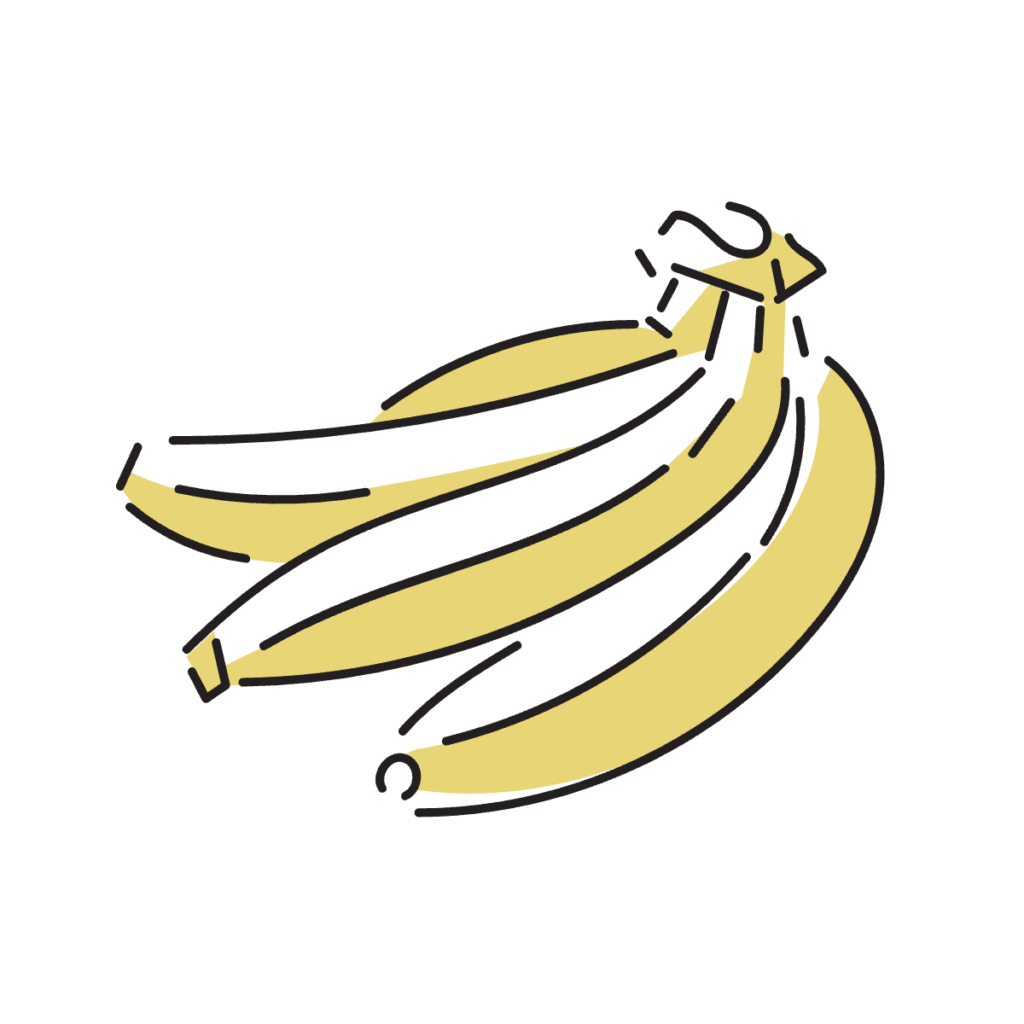
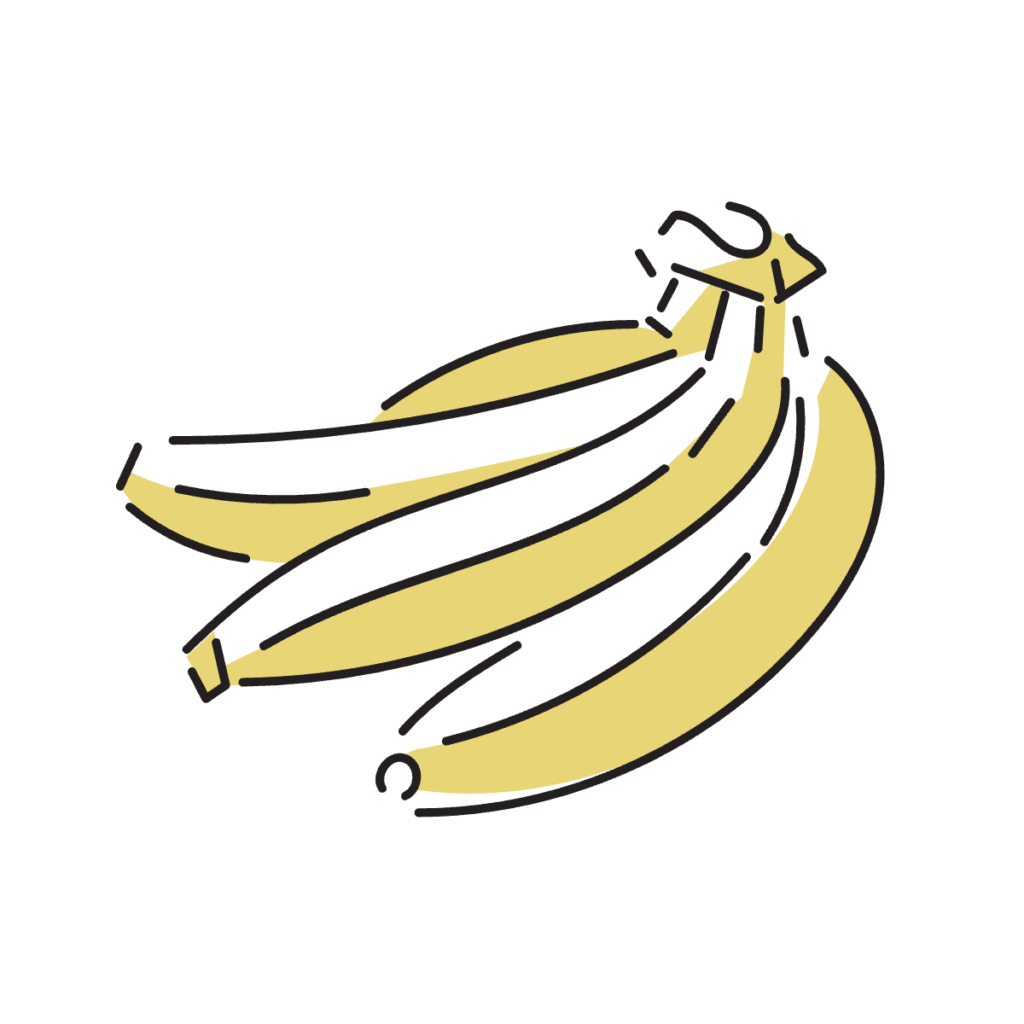
冷凍食品、レトルト、パン、バナナなど、準備に手間のかからないものを活用しましょう。
子どもが1人で食べられるものや、好きなものを優先するのもポイントです。
わが家では娘が小さいころは偏食がひどく、母乳と赤ちゃんせんべいだけの日もありました……。
主要都市などの対応エリアに住んでいれば、Uber Eatsや出前館などのフードデリバリーを利用することもできます。
とにかく手を抜けるところは抜いてしまいましょう!
3.テレビ・動画に頼る
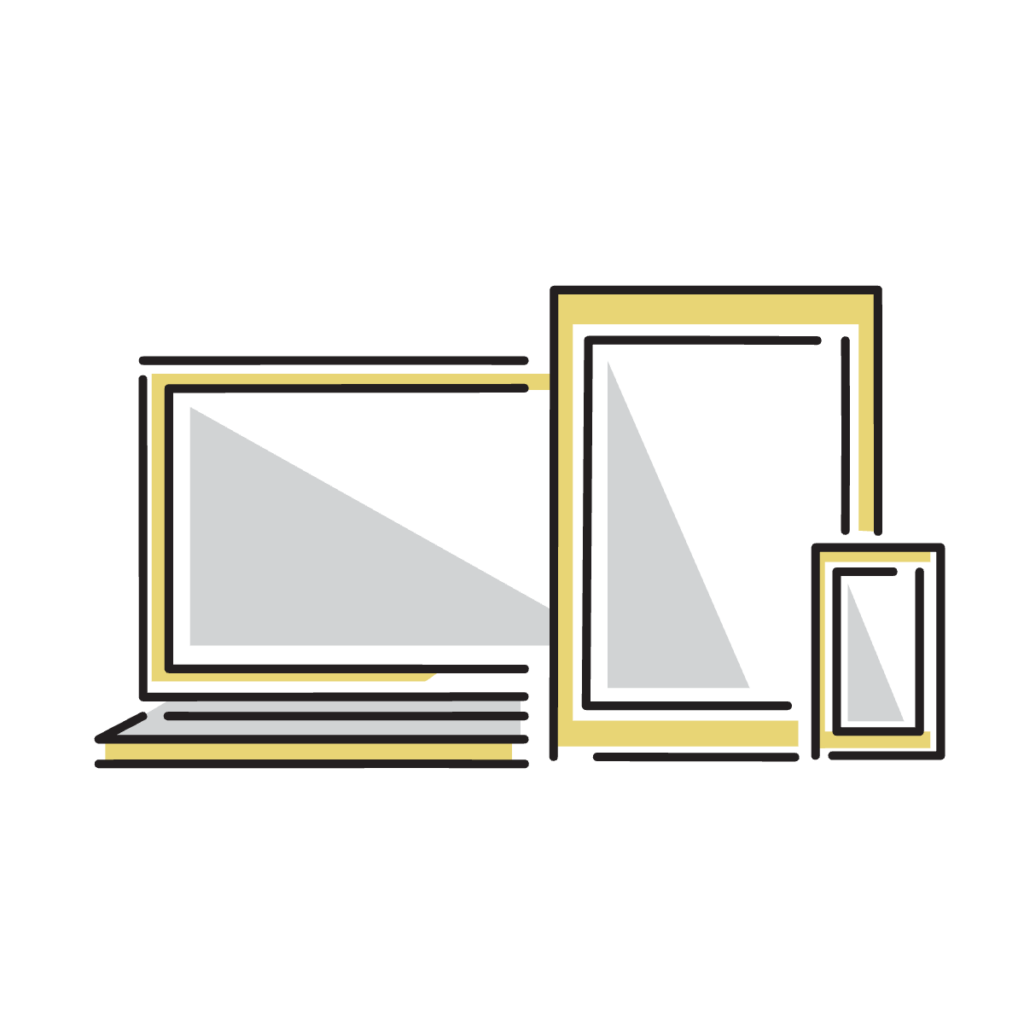
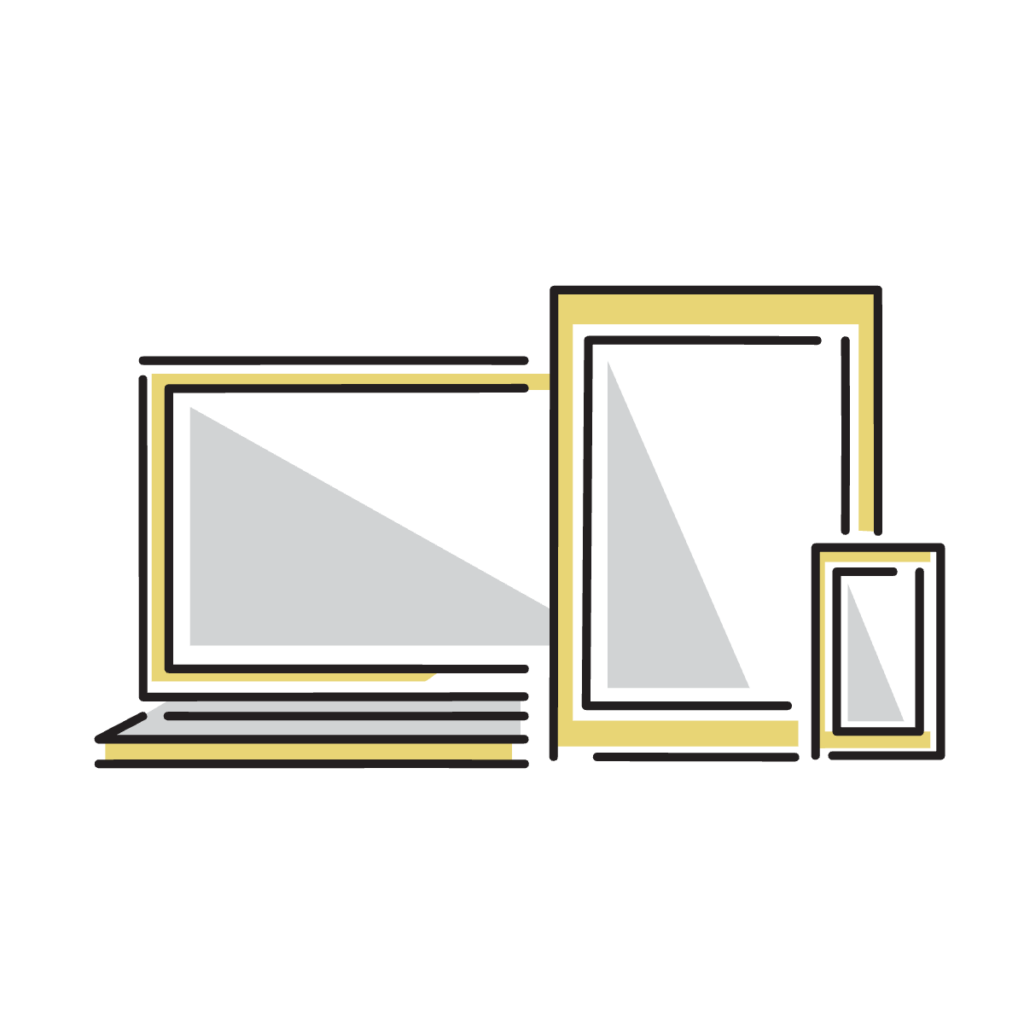
育児中のテレビや動画の活用は賛否両論ありますが、体調の悪い日は非常時モードとして割り切るのも大切です。
子どもにおすすめのテレビ・動画サービス
- NHK教育テレビ(Eテレ)
- 「おかあさんといっしょ」「いないいないばあっ!」「みいつけた!」など子どもの年齢や成長に合わせた内容が多い
- テレビ放送のほか、「NHKプラス」や「NHKオンデマンド」でも一部の番組がオンライン配信で視聴可能
- Amazonプライム・ビデオ(アマプラ)
- 「しまじろう」「きかんしゃトーマス」「おさるのジョージ」などのアニメを観ることができる
- キッズ向けの専用プロフィールを設定すると、子ども向けコンテンツだけが表示される機能がある
- YouTube
- 「ベビーバス」「ピンキッツ(Baby Shark)」「はたらくくるま」などの安全教育や童謡などの動画が多い
- 子ども向けに特化した「YouTube Kids」アプリを使えば、不適切なコンテンツが排除され、広告もほとんど表示されないため、通常のYouTubeに比べて安全性が高いとされている
※ただし、完全に安心できるわけではないので注意
- Netflix
- 「パウ・パトロール」「ペッパピッグ(Peppa Pig)」「スポンジ・ボブ」などが視聴可能
- 12歳以下の子ども向けに安全に視聴できる「キッズプロフィール」を作成できる
- Disney+(ディズニープラス)
- 「ミッキーマウスクラブハウス」「トイ・ストーリー」「アナと雪の女王」などディズニーやピクサー作品が豊富
ずっと動画を見せていることに罪悪感がある…と思う人もいるでしょう。
しかし罪悪感を抱く方の多くは、普段から子どもの動画視聴時間に気を配っている傾向にあると思います。
普段のルールを少し緩めて、自分も回復を優先しましょう。



実際に動画を通じて言葉を覚えたり、新しい知識を得ることもありますよ!
体調不良でもバタバタしない!発熱にそなえる5つの対策
ワンオペ育児中の発熱は突然襲ってくることがありますよね。
いざというときに困らないよう、できることから準備して、少しでも安心できる環境を作っておきましょう!
1. 風邪をもらわないための予防策
小さな子どもがいると、どれだけ気をつけていても風邪をもらってしまうことがあります。
完全に防ぐのは難しいけれど、日々のちょっとした予防で風邪をもらう頻度を減らすことができます。
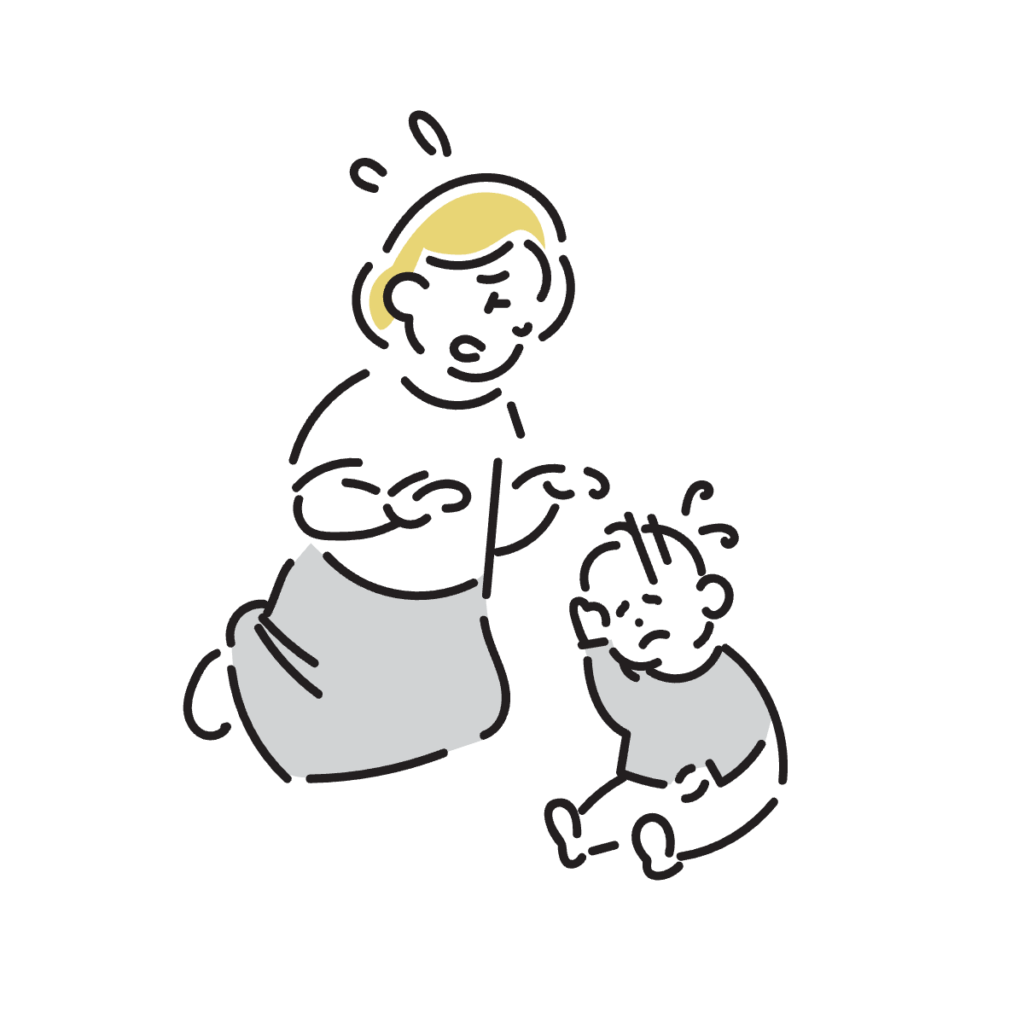
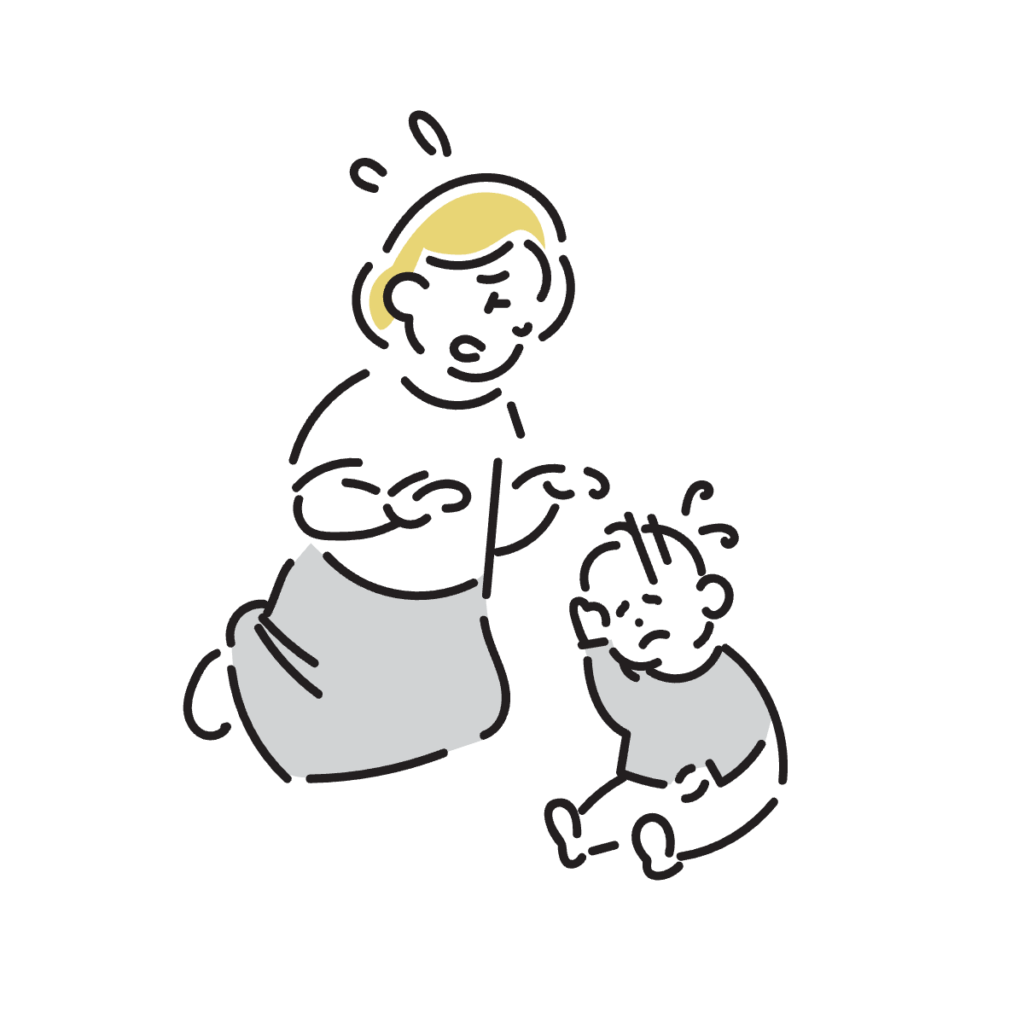
- 睡眠と栄養をしっかりとって免疫力を高める
- 手洗い・うがいをこまめにする
- タオルやコップは分けて使う
- 加湿器を活用して室内の湿度を保つ
- 定期的に換気をする
- 子どもの食べ残しは食べない
- 子どもが風邪を引いたら、自分は家でマスクをして過ごす



できる範囲で予防をして、少しでも元気に過ごせるようにしましょう!
子どもの風邪で小児科を受診するとき、自分にも症状があれば診てもらうのもおすすめです。
小児科によっては親の簡単な診察や処方にも対応してくれるところがあります。
早めのケアで重症化を防ぎましょう!
2.発熱セットを準備しておこう
発熱時にすぐ使えるアイテムを常備しておくと安心です。


発熱セット
- 水分補給アイテム
- 水、麦茶(カフェインレス)
- 経口補水液やポカリスウェット
- ゼリー飲料
- 体調が悪いときに食べやすいもの
- レトルトおかゆ
- 冷凍うどん、冷凍焼きおにぎり
- インスタントスープ(卵スープ・お味噌汁)
- プリン、ヨーグルト
- 子ども用のおやつ
- スティックパン
- バナナ
- ゼリー
- すぐに使える便利グッズ
- 氷枕
- 紙皿、紙コップ、割り箸(洗い物を減らす)
3.宅配サービス・ネットスーパーで備えよう


ワンオペ育児中は買い物に行くのもひと苦労……。そんなときに頼れるのが、宅配サービスやネットスーパーです。
日頃から食料や日用品をストックしておくことで、いざというときに慌てずに済みます。
- 大手スーパーのネットスーパー
- イオンネットスーパー、イトーヨーカドーなど
- 実店舗の商品をネットで注文して、近くの店舗から配送
- オンライン専用スーパー
- Amazonフレッシュ、OniGO
- など
- 実店舗を持たず、ネット販売に特化
- 即配サービスもあり便利
- 生協・宅配サービス
- コープ、Oisix(オイシックス)など
- 週1回の定期配送が可能で、食材の買い出しの手間を軽減
- ドラッグストア系のネット宅配
- ウエルシアネットスーパー、マツキヨココカラオンラインストア


- 食品・日用品・医薬品も一緒に購入できるので、体調不良時に便利
- ウエルシアネットスーパー、マツキヨココカラオンラインストア
オンライン専用スーパーは対応地域が限られている場合が多く、特に都心部で利用できるケースが多いです。
一方で大手スーパーのネットスーパー、生協・宅配サービスやドラッグストアの配送エリアは比較的全国どこでも利用しやすいため、地方在住の方でも使いやすいですよ。
4.冷凍ストックを活用して非常時に備える


冷蔵庫や冷凍庫にストックがあると、急に体調を崩して買い物に行けないときでも安心です。
特に大型冷凍庫があると、冷凍食品や作り置きのおかずをたっぷり備蓄でき、非常時の食事準備がスムーズになります。



わが家でも大型冷凍庫を購入したことで、業務スーパーなどで冷凍食品のまとめ買いができるようになり、とても便利になりました。
体調が悪くて「何も準備してない!」と焦らなくて済むように、日頃から少しずつ冷凍ストックを増やしておくのがポイントです。
5.子どもが安心して過ごせる環境づくり
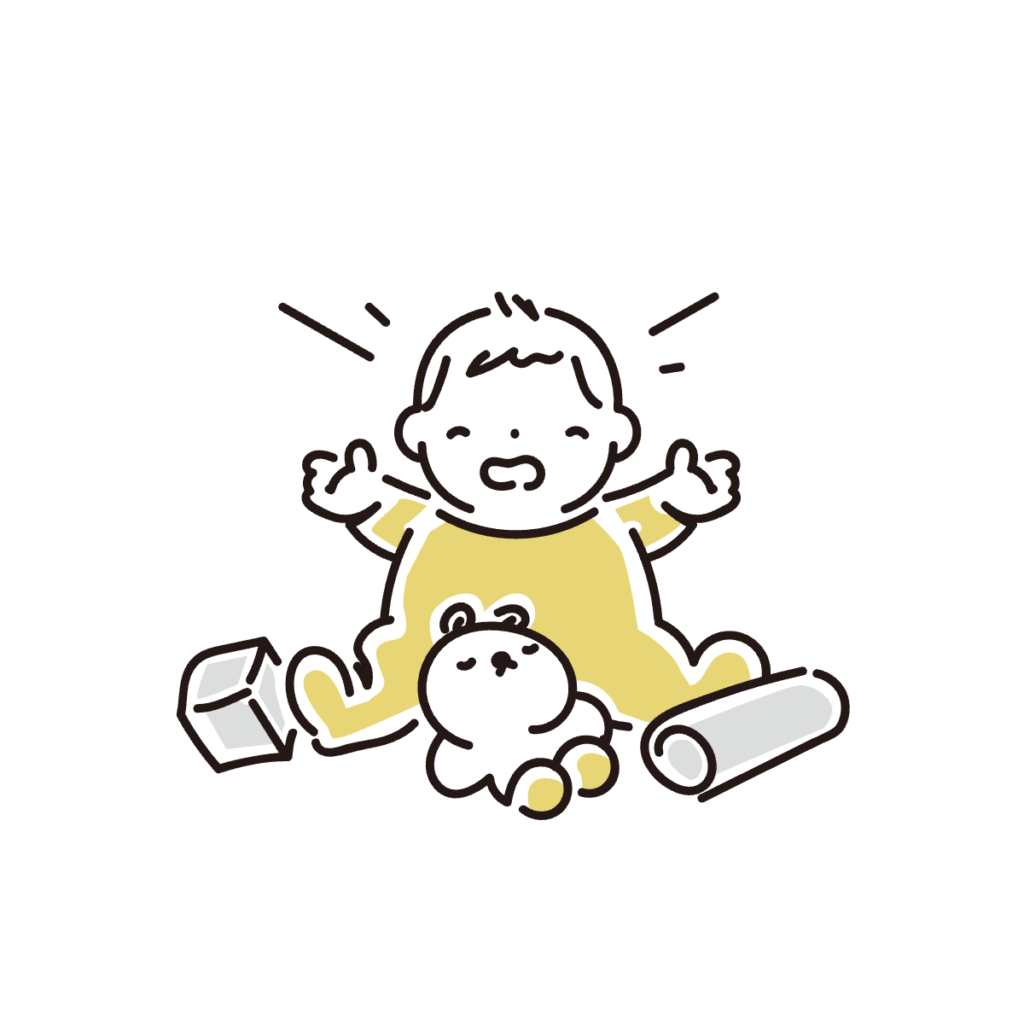
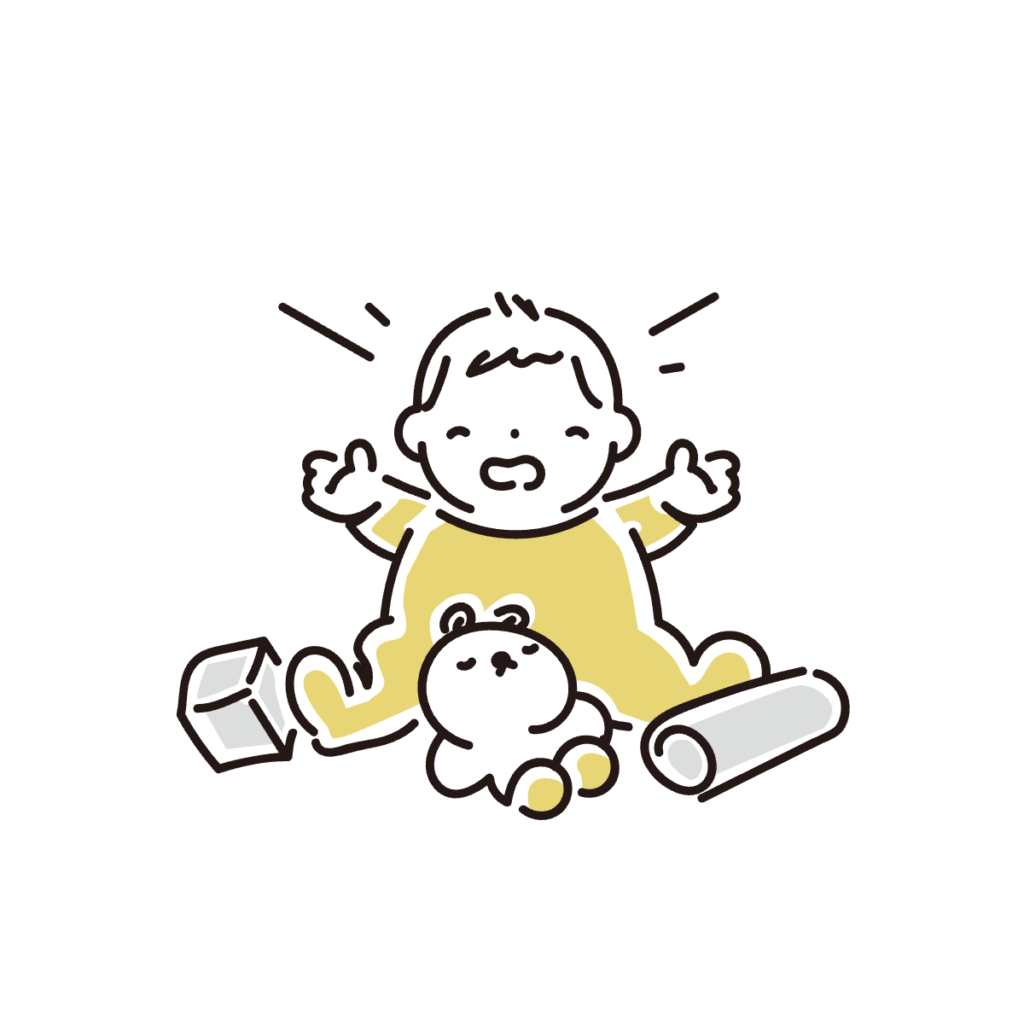
自分が寝込んでしまったときでも、子どもが1人で安全に過ごせるように、普段から準備しておきましょう。
特にワンオペ育児中は、突然の体調不良にも対応できる環境づくりが大事です。
基本の安全対策
- 危険なものは手の届かない場所へ
包丁や薬、洗剤など、絶対に触ってほしくないものは、高い場所やロック付き収納に入れる - ドアロックガードを活用する
引き出しや扉を自分で開けるようになったら、ドアロックガードを付けて中の物を取り出せないように - コードや電源タップを整理する
引っ張ってしまわないように、コード類はまとめて隠し、コンセントカバーをつけて感電リスクを防ぐ
安心して遊べる環境づくり


🌱お気に入りのおもちゃや絵本を準備する
わが家では子ども2人とも こどもちゃれんじ を受講していました。
年齢に合ったおもちゃが届くので、誤飲の心配が少なく、安心して遊ばせることができました。
🌱シールブックや塗り絵を用意しておく
100円ショップで購入できるシールブックや塗り絵は、緊急時に大活躍!
事前に用意しておくといざというときに役に立ちます。
🌱久しぶりのおもちゃで興味を引く
しばらく遊んでいないおもちゃを目の届かない場所にしまっておき、体調不良時に出すと、子どもが新鮮に感じて長時間遊んでくれますよ!
番外編.いざというときに頼れる先をチェック


これまでワンオペでも乗り切れる対策をいくつかご紹介しました。
とはいえ、体調が悪くてどうにもならないときがあります。
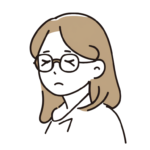
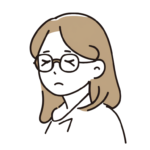
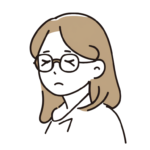
もう無理!どうしたらいいの?
そんなときこそ、ひとりで抱え込まないために、普段から頼れる人やサポート先を把握しておくことが大切です。
いざというときの安心感が変わります。
近所や友人の助けも大切に!
頼れる人がいない状況だったからこそ、仲良くなったママ友が「いざとなったら子どもを見てあげるよ」と言ってくれたのは心強かったです。
まさに遠くの親戚より近くの他人。頼れる人が少ないからこそ、日頃から近所のつながりを大切にしておきたい ですね。


行政の育児サポートを活用しよう!
ファミリー・サポート・センターや一時預かりなど、自治体の育児支援サービスを事前にチェックしておくと安心です。
これらのサービスは地域によって内容や料金が異なるため、住んでいる自治体の公式サイトや窓口で確認しておきましょう。
また、子どもも自分も元気なうちに登録だけしておくと いざというときにスムーズに利用できます!
オンライン診療の活用
オンライン診療は、スマホやパソコンを使って自宅で診察を受けられる サービスです。
主なオンライン診療サービス
- CLINICS(クリニクス)
→ 初診からオンライン診療が可能。5000件以上の医療機関と連携。
- SOKUYAKU(ソクヤク)
→ 38以上の診療科に対応し、オンライン診療後に薬の宅配までセットで手配できる。
- curon(クロン)
→ 子どもの診察もアカウントを連携させて予約・受診が可能。



体調が悪いときに、子どもを連れて病院に行くのは本当に大変。そんなときにとても便利です。
まとめ
ワンオペ育児中の発熱は本当に大変ですが、事前の準備や日頃の対策で乗り切ることができます。
無理はせず最低限のことだけこなし、あとはしっかり休むのが一番です。
🌱発熱時のポイント
- お風呂は無理せずお休みし、蒸しタオルやおしりふきで対応
- ご飯はレトルトや冷凍食品、宅配サービスをフル活用
- テレビや動画を上手に活用し、無理なく過ごせる工夫を
- できるだけ横になり、早めの回復を最優先
🌱普段から備えておきたいこと
- 風邪予防を徹底して、体調を崩しにくい環境を作る
- 発熱セット(経口補水液・解熱剤・レトルト食品など)を常備
- 宅配サービスや大型冷凍庫を活用して、食料や日用品をストック
- 危険なものを片付け、子どもが1人でも安全に過ごせる環境を作る
- 緊急時に頼れる先(ファミサポ・一時保育・近所の助けなど)を把握しておく
自分を大切にすることもワンオペ育児の一部
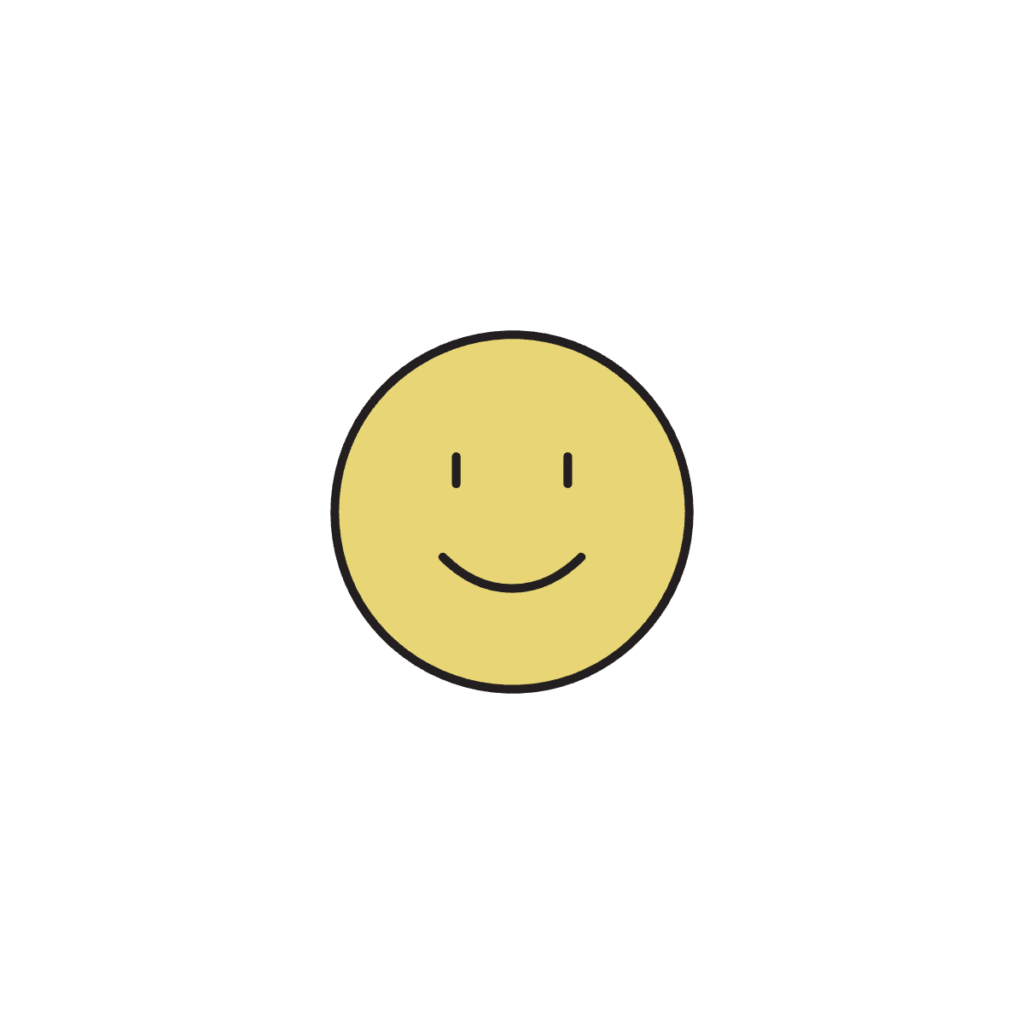
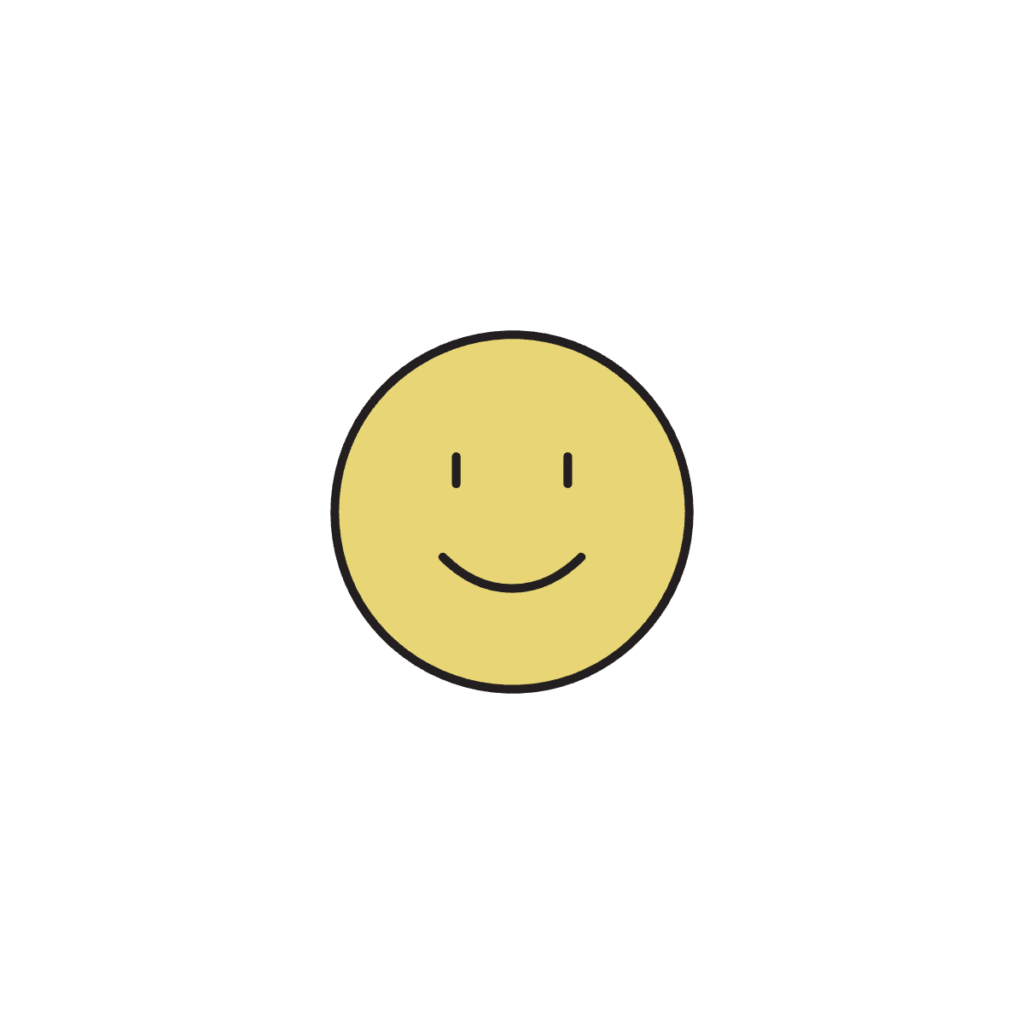
自分が体調を崩してしまっては、育児も家事も思うようにできません。
ワンオペ育児はつい頑張りすぎてしまいがちですが、無理をせず、休むことも大切です。
少し疲れたな……と感じたら、思い切って手を抜いたり、周りに頼ったりする勇気を持ちましょう。
🌱あなたが心身ともに元気でいることが、何よりも大切です。
どうか自分を大切にしてくださいね。